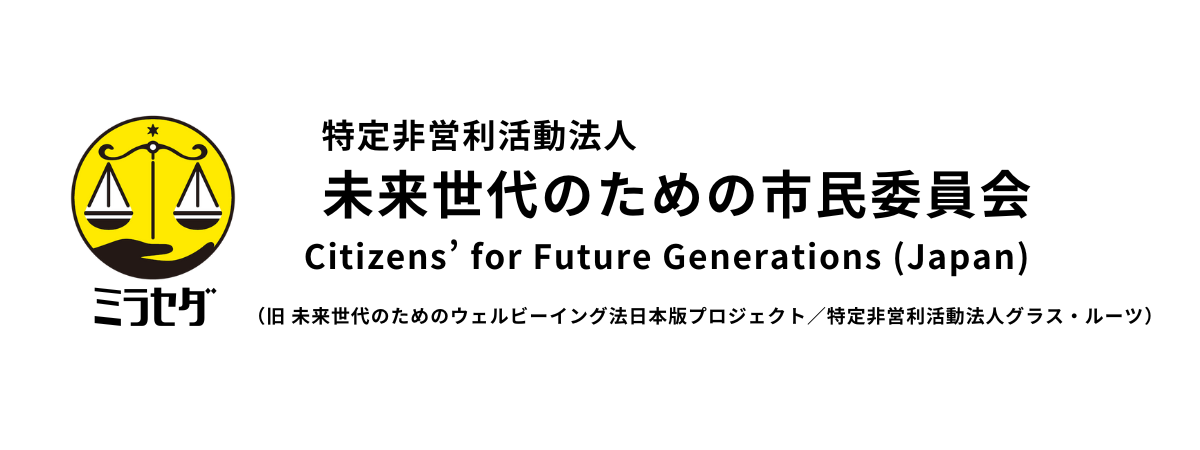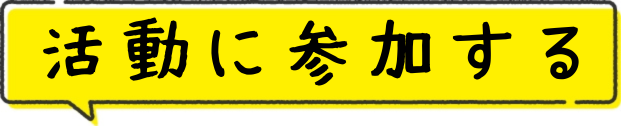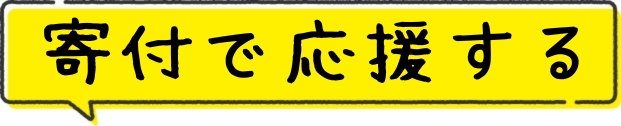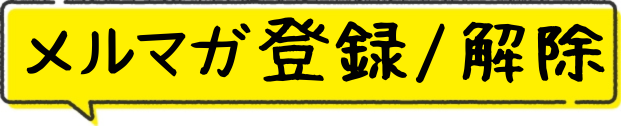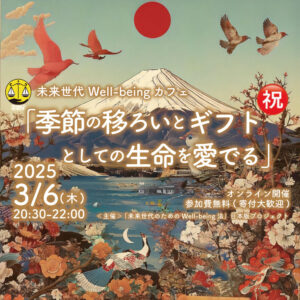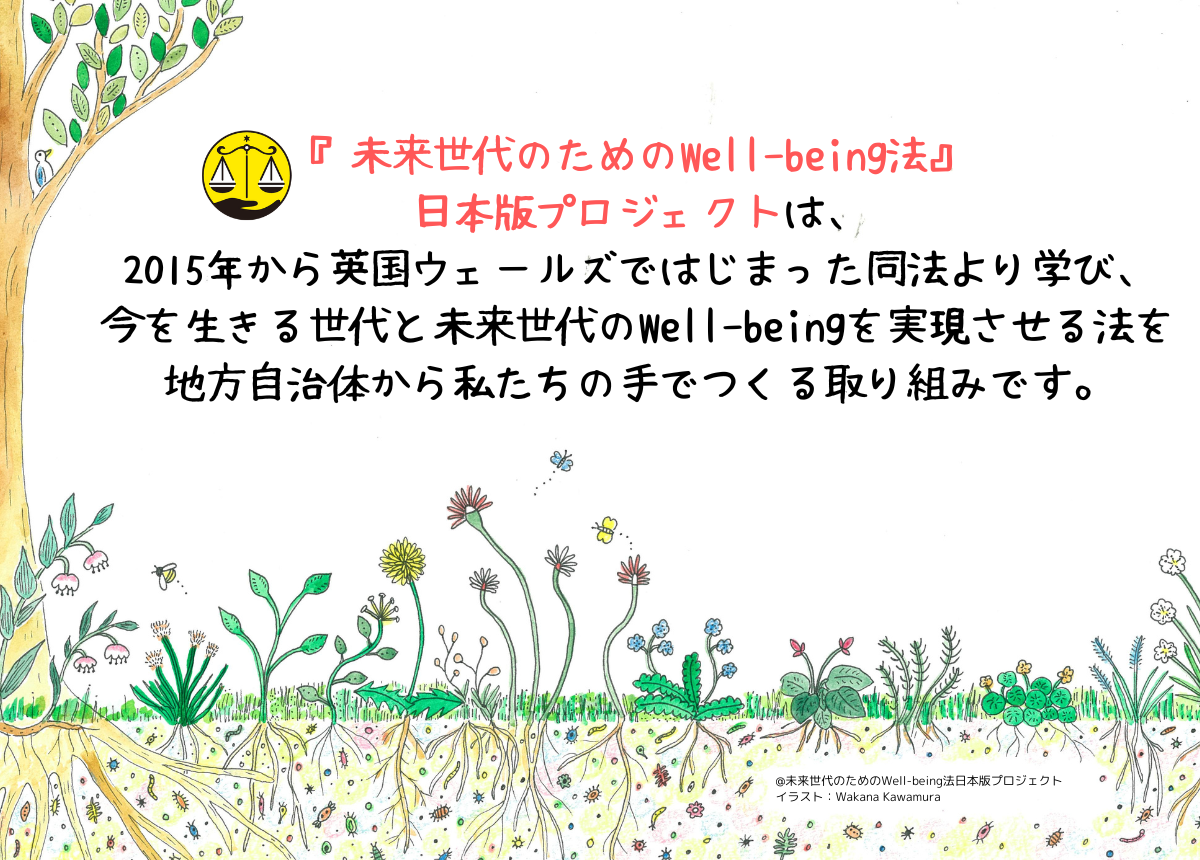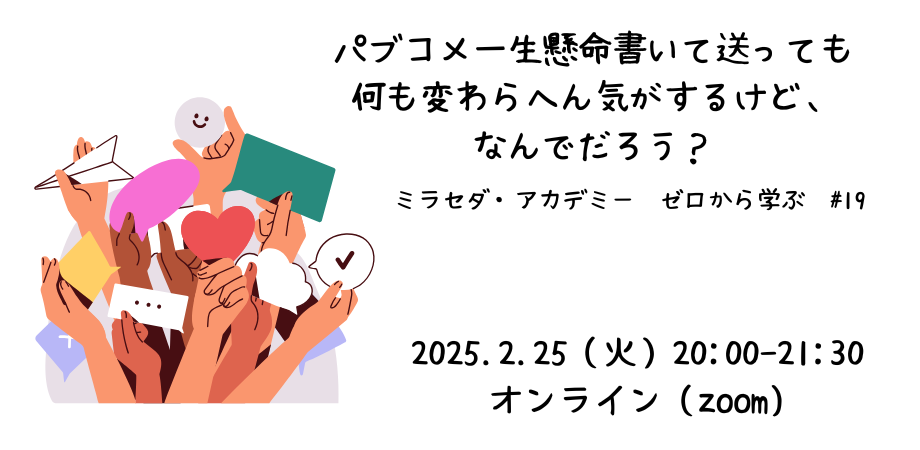
パブコメ一生懸命書いて送っても何も変わらへん気がするけど、なんでだろう?
〜ミラセダ・アカデミー ゼロから学ぶ #19
2025.2.25(火)20:00-21:30オンライン(zoom)
---------------------
みなさんは、パブリックコメントって書いたことはありますか?
私自身は、パブリックコメントという言葉を聞いたことはあっても、自分で書いて出すということに参加しだしたのはこの2年弱のことです。
2322年5月。岸田元首相が突如として発表したGX実行会議。
同年7月には、第一回GX実行会議が招集され、12月に法案がまとまるまでに11回の実行会議を経て、
年末12/23からパブコメが募集されたとき(こういう大事なパブコメって、ほぼ年末年始挟んでくるよね、、、)
仲間が作ってくれたパブコメセミナーに連日専門の方が来てくださり、
最後の一週間くらいは、毎晩zoomをつないでいて、一緒にパブコメ書いて出す。
最終日は、23:59の締切まで、ギリギリまで送信ボタンを押してフィニッシュしたときには、みんなで声を上げました。
この経験は、私にとってのパブコメのハードルを大きく下げてくれて、
そのあとは、一人でも書いて出せるようになりました。
気がつくようになってみたら、パブコメっていうのはほんとにしょっちゅう、あらゆる分野に関して募集されていて、
全部に対応することはとてもじゃないからできないんだけど、
その気になれば、年間通して、国民が意見を述べる機会や場は用意されている。
国民(市民)が、政治に参加する機会は選挙だけではなくて、ほんとに途切れることなく機会があるということを知るようになりました。
そうして、自分が「これは書かなきゃ!」って思う案件の時は、にわか勉強でもゼロよりはまし!と言い聞かせて、とにかく学び、アウトプットとして書いてみる。
それは、自分をとても成長させてくれたとも思いますし、GX法案後の日本は、原発事故以降の日本の大転換のタイミングでもあったと思い、原子力政策やエネルギー政策、気候変動などの関連でも、大きなパブコメというのはいくつも続きました。
今 この文を2/16の午前中に書いています。
昨年年末年始にも、エネルギー基本法案はじめ関連法案4つのパブコメがあり、第七次エネルギー基本法案のパブコメには、4万件を超える意見が集まったと聞いています。
まだその報告もWEBページ上には報告上がってないですが、すでに2/18には閣議決定されると聞こえてきています。
パブコメって、確かに国民(市民)が意見を出せる機会ではあるのだけれど、
でも、「ほんとにちゃんと読んでくれてるの?」とか、「書いても無駄だよね、、、意見が採用されたような気がした時がない!」とか、
そう思う人って多いんじゃないかと思うのです、、、
それってどうしてだろう?
そもそも、法律ではパブコメのことをどう規定してるんだろう?って疑問が湧いて、ちょっと調べてみました。
今回は、そんなことを題材にゼロから学んでみます。
先にちょっと予習しときたい人は、「行政手続法 第六章」を探して読んでみてください。
予習は、してもしなくても大丈夫です。
ゼロから学んで、そして「どうしたら、市民の意見が政策決定に反映されるようになるだろう?」ってことを一緒に考えたいと思います。
ナビゲーター:きら/河合 史惠
アクティビスト。京都市右京区在住。
世界中の誰もが十分な選択権と尊厳をもつ世界を願い活動する。
ベースに、未来世代のためのウェルビーイング法、パーマカルチャー、NVC、深層民主主義、熟議民主主義を学び実践することを置く。
未来世代のためのウェルビーイング法日本版プロジェクト主宰。
特定非営利活動法人グラス・ルーツ代表理事。
----------------
パブコメ一生懸命書いて送っても何も変わらへん気がするけど、なんでだろう?
〜ミラセダ・アカデミー ゼロから学ぶ #19
2025.2.25(火)20:00-21:30オンライン(zoom)
参加費:無料(ご寄付にご協力いただけると、とってもありがたいです!)
-----------
主催:未来世代のためのウェルビーイング法日本版プロジェクト
英国・ウェールズで2015年から施行され、世界ではじめて これから生まれてくる未来世代の人権を認め、持続可能な開発(SDGs)を達成することを国内法としてまとめた、「Well-being of Future Generations Act(日本語訳:未来世代のためのウェルビーイング法日本版プロジェクト、略称:未来世代法)」から学び、日本の 主に地方議会に紹介し、行政の仕組みの中で実際に使っていただけるようになることを目指し活動しています。
未来世代法から学ぶ とは、●長期的視点 ●予防原則 ●市民意見の政策への反映と協働 ●部署や立場の違いを超えた横断的協働 ●情報公開 などを、あたりまえのこととしていくことを目指しています。
.